【前編】枝分かれは宗教の常?派生する真言宗・十八山編
関連キーワード

空海により日本で隆盛を極めた密教。そして、真言宗。密教や真言宗のおさらいをまずさせていただきます。
【密教】
経文はあれど、文字よりも口伝や曼荼羅で伝えるのがモットーです。トップは大日如来。
【胎蔵界】
大日如来の慈悲や真理の側面。曼荼羅では各区画を「院」と表します。
【金剛界】
大日如来の智慧の側面で、煩悩を砕きます。曼荼羅では各区画を「会」と表します。
【空海】
真言宗開祖。非凡な才能とたゆまぬ修行で密教を修め、帰国しました。
【古義・新義】
念仏を唱えるのが古義。新義は三密加地を特に重要視。心に大日如来を描き、念仏を唱えることで、降りてきてくださる、という物です。
【小野流・広沢流】
別名野沢(やたく)。それぞれ六流派ずつ存在します。小野流は口伝重視、広沢流はそれまでの密教の規律等を重視した、いわば保守派。
【密教】
経文はあれど、文字よりも口伝や曼荼羅で伝えるのがモットーです。トップは大日如来。
【胎蔵界】
大日如来の慈悲や真理の側面。曼荼羅では各区画を「院」と表します。
【金剛界】
大日如来の智慧の側面で、煩悩を砕きます。曼荼羅では各区画を「会」と表します。
【空海】
真言宗開祖。非凡な才能とたゆまぬ修行で密教を修め、帰国しました。
【古義・新義】
念仏を唱えるのが古義。新義は三密加地を特に重要視。心に大日如来を描き、念仏を唱えることで、降りてきてくださる、という物です。
【小野流・広沢流】
別名野沢(やたく)。それぞれ六流派ずつ存在します。小野流は口伝重視、広沢流はそれまでの密教の規律等を重視した、いわば保守派。
東寺真言宗
教王護国寺が総本山。空海が開いた本家本元です。
嵯峨天皇に下賜された東寺を「見っ卿の道場にしよう」と実行したもの。落雷などで焼けたり明治時代には金峰寺と教王護国寺を修行場とする古義、長谷寺と智積院を本山とする新義と二派に分裂したりと結構苦労人、いや苦労寺。1946年には本来の東寺真言宗として統合されました。国宝の仏像や五重塔、金堂などがあります。
嵯峨天皇に下賜された東寺を「見っ卿の道場にしよう」と実行したもの。落雷などで焼けたり明治時代には金峰寺と教王護国寺を修行場とする古義、長谷寺と智積院を本山とする新義と二派に分裂したりと結構苦労人、いや苦労寺。1946年には本来の東寺真言宗として統合されました。国宝の仏像や五重塔、金堂などがあります。
高野山真言宗
金剛峯寺が総本山。成立は東寺よりも後になります。「高野山を戴きたく存じます」「よろしい」ということで、これまた嵯峨天皇より下賜された物。鳥羽上皇や藤原道長など、そうそうたる面々が信仰したため発展。江戸時代に火災に遭うも、不動明王の御堂、金剛三昧院多宝塔など国宝あり。元は古義でしたが、11世紀頃、時の和尚覚鑁が山を下り、新義真言宗を生み出すきっかけとなりました。
善通寺派
善通寺を総本山とします。古義の真言宗。小野流の創始者、仁海和尚が曼荼羅寺を創設。数多くの名僧を輩出しています。
善通寺派大本山
大本山とは、総本山に次ぐいわゆるナンバーツーのお寺。寺社は随心院といいます。江戸時代には幕府の庇護を受けていました。一説によると小野小町がこのお寺に住んでいたらしく、ゆかりの品もあるそうです。
醍醐派
醍醐寺にあります。空海の弟を師匠に持つ理源大師により創設。醍醐天皇がよく勅願に訪れたそうで、この名前。地震や山火事という天災に見舞われますが、皇室や大綱秀吉公により復興を遂げています。修験道の一派も絡んでいる模様。
御室派
光孝天皇が作り始めますが、途中で崩御。宇多天皇が後をついで、そのまま派祖となります。古義にして、広沢流。一時は広沢流のまとめ役でした。自社は仁和寺。派祖が上皇だけあって、元号からとったようです。
大覚寺派
元嵯峨天皇の別荘をお寺にした、セレブ派です。皇室がパトロンとなって門跡を務め、後宇田上皇に至っては「ワシ、大覚寺で院政やるからね」と言い、政にも関係深いお寺となりました。古義に属します。
泉涌寺派
密教だけでなく禅宗などの四つの宗派をごった煮的に学ぶ場所だったようです。創始者は空海とされますが、月輪大師ともされています。運慶作と思われる釈迦、阿弥陀、弥勒如来像あり。
真言宗山階派
醍醐天皇が母の為に建てたとされるのが勧請寺(大本山)。千手観音が本尊です。皇室のみならず、藤原氏とも関係深いお寺。








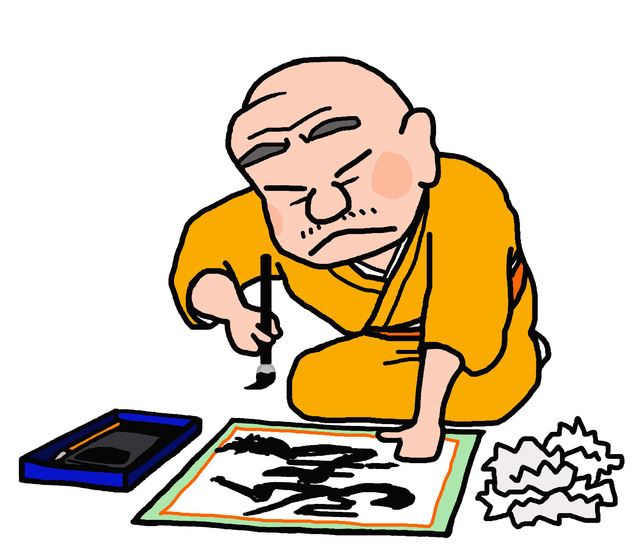















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

