愛別離苦、苦しみにピリオドを打つ方法
関連キーワード

四苦八苦という言葉があります。
生きて、老いて、病気になって、死ぬ四苦に加え、更に四つの苦を加えることで合計八苦となりました。
しかし何故「四苦八苦」とわざわざ分けて四字熟語にしているのでしょうか。呼びやすいから?そんな単純な理由だけではありません。
初めの四苦はいわば生物としての本能的な苦しみであり、残りの四つは人間だけが持つ感情や煩悩から来るものなのです。愛別離苦(あいべつりく)、怨憎会苦(おんぞうえく)、求不得苦(ぐふとくく)、五蘊盛苦(ごうんじょうく)が内訳になります。
生きて、老いて、病気になって、死ぬ四苦に加え、更に四つの苦を加えることで合計八苦となりました。
しかし何故「四苦八苦」とわざわざ分けて四字熟語にしているのでしょうか。呼びやすいから?そんな単純な理由だけではありません。
初めの四苦はいわば生物としての本能的な苦しみであり、残りの四つは人間だけが持つ感情や煩悩から来るものなのです。愛別離苦(あいべつりく)、怨憎会苦(おんぞうえく)、求不得苦(ぐふとくく)、五蘊盛苦(ごうんじょうく)が内訳になります。
他の苦と毛色が違う愛別離苦
これらの苦の中でも、愛別離苦は毛色が違っています。
他の苦は「あいつは嫌い」「欲しいけど手に入らない」「生きていることが自体苦しい」といったものですが、愛別離苦とは愛する者との別れのことです。
五蘊盛苦が苦の中でも最たるものと言えますが、愛別離苦は他者との断ち切り難い未練を伴っています。
求不得苦は基本的には自分だけの問題です。
他者の心が絡む点では怨憎会苦と似ていますが、相手と縁を切りたい怨憎会苦は離れられればスッキリするのに対し愛別離苦は離れる前も、離れてからも辛いのです。
他の苦は「あいつは嫌い」「欲しいけど手に入らない」「生きていることが自体苦しい」といったものですが、愛別離苦とは愛する者との別れのことです。
五蘊盛苦が苦の中でも最たるものと言えますが、愛別離苦は他者との断ち切り難い未練を伴っています。
求不得苦は基本的には自分だけの問題です。
他者の心が絡む点では怨憎会苦と似ていますが、相手と縁を切りたい怨憎会苦は離れられればスッキリするのに対し愛別離苦は離れる前も、離れてからも辛いのです。
一切皆苦を知る
お釈迦様が弟子たちに告げた一切皆苦とは、「この世には苦しかないよ」との非常とも言えるものです。
逃げ出したくなることばかりですが、その事実、苦から逃げては何の意味もありません。
たとえるなら虫歯です。無視して放置したらひどくなるばかりです。多少痛い思いをしても、ドリルの音が怖くても、ちゃんと治療をすれば歯は健康さを取り戻します。
逃げ出したくなることばかりですが、その事実、苦から逃げては何の意味もありません。
たとえるなら虫歯です。無視して放置したらひどくなるばかりです。多少痛い思いをしても、ドリルの音が怖くても、ちゃんと治療をすれば歯は健康さを取り戻します。
子を失った母

その昔、子供を失くした母がいました。その嘆きようは激しく、周りが「諦めよう」と言っても生き返らせる方法を探します。
そんな時お釈迦様に出会いました。
お釈迦様は言います。「芥子の実をもらってきなさい。ただ、死者を出したことのない家からでないと駄目だからね」芥子の実はどの家にもあったけれど、死者を出したことのない家は結局見つからず。死は避けられないことをその母親は悟って仏門に入ったとのことです。
我が子をなくすことはまさに愛別離苦の代表的な事例と言えましょう。しかしお釈迦様は慰めるのではなくその事実と向き合わせ、「どうにもならないことはある。でも前に進むしかない」ことを語らずに教えたのです。
そんな時お釈迦様に出会いました。
お釈迦様は言います。「芥子の実をもらってきなさい。ただ、死者を出したことのない家からでないと駄目だからね」芥子の実はどの家にもあったけれど、死者を出したことのない家は結局見つからず。死は避けられないことをその母親は悟って仏門に入ったとのことです。
我が子をなくすことはまさに愛別離苦の代表的な事例と言えましょう。しかしお釈迦様は慰めるのではなくその事実と向き合わせ、「どうにもならないことはある。でも前に進むしかない」ことを語らずに教えたのです。
まとめ
少し考え方を変えればいくらでも世界は変わります。愛する人を失うことは辛いことですが、いつまでもううずくまって泣いては前に進めませんし、何も見えなくなります。
勇気を持って立ち上がり、逃げることなく前に歩いていきましょう。向き合って乗り越えたら、世界が違って見えてきます。
勇気を持って立ち上がり、逃げることなく前に歩いていきましょう。向き合って乗り越えたら、世界が違って見えてきます。








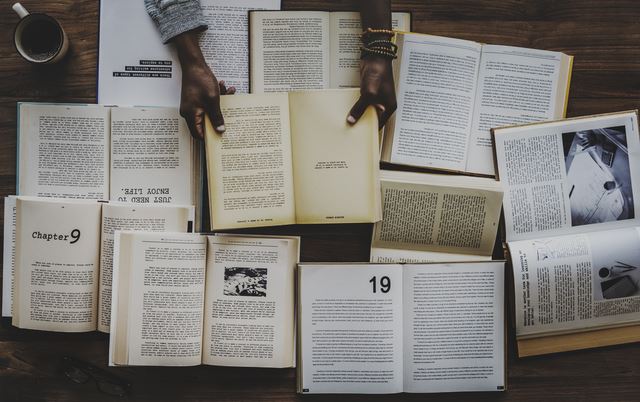













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

