備えあれば憂いなし
関連キーワード

意味
普段から準備をしていれば、いざというときに対応がしっかりとできるということ。
日ごろから準備や対策をしていれば、何かが起こっても心配いらないということ。
日ごろから準備や対策をしていれば、何かが起こっても心配いらないということ。
由来
古代中国の書物である「春秋左氏伝」のなかでは、殷の国の宰相であった傳説の言葉で「これ事を事とする(するべきことをしておく)乃ち其れ備え有り、備えあれば患い無し」とあります。ここでいう「患い」とは「憂い」のことで、「心配」「不安」「災い」というような意味があります。
また、「書経」のなかでは
「書曰、居安思危、思則有備、有備無憂」とあり、
「書にいわく、安きに居りて危うきを思う、思えば則ち備え有り、備え有れば憂い無し」
となります。これは、
「安全な状態でも危険なときのことを考える。考えればそれに対して備えをするようになる。備えていれば何も心配はいらない」ということです。これは国内外の戦争が続いた中国や国内での争いが続いた日本では貴重な言葉として使用されてきました。
また、この考え方は欧米でも同様で、英語表現に、
Providing is preventing.
(供給することは防止することである)
Keep something for a rainy day.
(まさかのときに備えて貯蓄せよ)
Lay by something for a rainy day.
(雨の日のために何かを貯えておけ)
Hope for the best but prepare for the worst .
(最善を願いながら、最悪に備えよ)
Better safe than sorry.
(後悔するより、安全な方がいい)
など多数あります。どれも平穏な時期からもしものときのために準備をしておくことをすすめたものです。
「最善を願いながら最悪に備える」というのは古代ローマの政治家であったセネカの言葉で、常に前向きでありながらも最悪の事態に備えるという政治家としての思考がよく表現されています。
また、「書経」のなかでは
「書曰、居安思危、思則有備、有備無憂」とあり、
「書にいわく、安きに居りて危うきを思う、思えば則ち備え有り、備え有れば憂い無し」
となります。これは、
「安全な状態でも危険なときのことを考える。考えればそれに対して備えをするようになる。備えていれば何も心配はいらない」ということです。これは国内外の戦争が続いた中国や国内での争いが続いた日本では貴重な言葉として使用されてきました。
また、この考え方は欧米でも同様で、英語表現に、
Providing is preventing.
(供給することは防止することである)
Keep something for a rainy day.
(まさかのときに備えて貯蓄せよ)
Lay by something for a rainy day.
(雨の日のために何かを貯えておけ)
Hope for the best but prepare for the worst .
(最善を願いながら、最悪に備えよ)
Better safe than sorry.
(後悔するより、安全な方がいい)
など多数あります。どれも平穏な時期からもしものときのために準備をしておくことをすすめたものです。
「最善を願いながら最悪に備える」というのは古代ローマの政治家であったセネカの言葉で、常に前向きでありながらも最悪の事態に備えるという政治家としての思考がよく表現されています。
意味の変遷
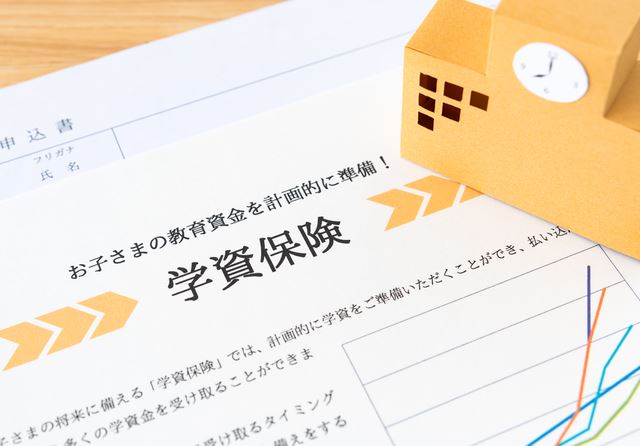
現在では何かあったときのために普段から備えておくという考え方から保険会社や警備会社などでキャッチコピーとして使用されることが多くなっています。日常生活においては会社で大きな仕事が特にない時期、試験が遠い学生などに注意を促すために使用されることが多く、予防線としての意味合いが強くなっています。そのため実際に大きな災害があるかどうかは明確ではありません。
使用法、使用例
「なんだ、どうしたんだ?こんなに大量の防犯グッズばかり買って」
「備えあれば憂いなしって言うからな。普段からの意識が重要なのさ」
「備えあれば憂いなしって言うからな。普段からの意識が重要なのさ」
似た意味のことわざ
「転ばぬ先の杖」「後悔先に立たず」「濡れぬ先の傘」など似た意味のことわざが多いことも特徴と言えます。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

