国宝・城-姫路城、彦根城、犬山城、松本城、松江城
関連キーワード

現在日本には国宝に認定されている城が5つあります。姫路城、彦根城、犬山城、松本城、松江城の5つです。ここでは、そのうちのいくつかにスポットを当てて紹介していきます。
姫路城
日本でもっとも美しい城はどこか?この質問に対して多くの人は青い空に白く輝く姫路城と答えるでしょう。日本において世界文化遺産登録第一号であり、「ミシュラン」による日本の観光施設評価で最高の三ツ星を獲得した城でもあります。
室町時代に原型が築かれ、戦国時代に羽柴秀吉が三重の天守を完成させました。それを現在のような五重六階の姿に改築したのは徳川家康の娘婿・池田輝政で、1601年から8年の歳月をかけて完成させました。輝政は山陽道を往来する人に最も美しく見えるようにこだわりをもって天守を築いたといわれています。
その姫路城でもっとも注目すべきは、やはり天守群の美しさです。壮麗な大天守・西小天守・乾小天守・東小天守からなる天守群が渡櫓(多聞櫓)で連結されて見事に調和し、非常にすぐれた構成美を見せています。この当時としては革新的な天守構成を「連立式天守」といいます。
大天守のフォルムも注目に値します。天守と石垣の高さはおおむね「二対一」で、ほどよいバランスで落ち着きがあります。また、天守の姿は上層に行くにつれて一定の逓減率で狭く細くなっています。この計算され尽くしたフォルムが、スマートに聳える雄姿を演出しているのです。
「白鷺城」という別名の由来となった真っ白な外観もまた、美しいと評価されます。城の色は武威を示す「黒」が主流でしたが、姫路城はそれとは正反対の「白」を採用しています。大量の白漆喰を壁に塗り(白漆喰総塗籠造)、全体を真っ白な色彩に仕立てています。このことから、それまでにない新たな価値観を創出しようとする輝政の美意識がうかがえます。
姫路城では2009年から大天守の改修工事に入り、壁面と屋根の漆喰の塗り直しが行われました。それまでの黒ずみがなくなり強烈な白になっているために違和感を訴える人がでるほどである。
室町時代に原型が築かれ、戦国時代に羽柴秀吉が三重の天守を完成させました。それを現在のような五重六階の姿に改築したのは徳川家康の娘婿・池田輝政で、1601年から8年の歳月をかけて完成させました。輝政は山陽道を往来する人に最も美しく見えるようにこだわりをもって天守を築いたといわれています。
その姫路城でもっとも注目すべきは、やはり天守群の美しさです。壮麗な大天守・西小天守・乾小天守・東小天守からなる天守群が渡櫓(多聞櫓)で連結されて見事に調和し、非常にすぐれた構成美を見せています。この当時としては革新的な天守構成を「連立式天守」といいます。
大天守のフォルムも注目に値します。天守と石垣の高さはおおむね「二対一」で、ほどよいバランスで落ち着きがあります。また、天守の姿は上層に行くにつれて一定の逓減率で狭く細くなっています。この計算され尽くしたフォルムが、スマートに聳える雄姿を演出しているのです。
「白鷺城」という別名の由来となった真っ白な外観もまた、美しいと評価されます。城の色は武威を示す「黒」が主流でしたが、姫路城はそれとは正反対の「白」を採用しています。大量の白漆喰を壁に塗り(白漆喰総塗籠造)、全体を真っ白な色彩に仕立てています。このことから、それまでにない新たな価値観を創出しようとする輝政の美意識がうかがえます。
姫路城では2009年から大天守の改修工事に入り、壁面と屋根の漆喰の塗り直しが行われました。それまでの黒ずみがなくなり強烈な白になっているために違和感を訴える人がでるほどである。
松本城
北アルプスの麓に建つ松本城は、関東甲信越で屈指の名城です。室町時代の守護・小笠原氏が築いた深志城を前身とし、1582年にこの地に入った石川数正が1594年から築城を開始、子の康長が完成させました。
この城の最大の見どころは、やはり現存天守でしょう。五重六階の現存天守としては最も古く、本来の黒漆塗りの下見板張による「黒い天守」を堪能できます。青い空・白い北アルプスと黒い天守が織り成す情景は息をのむ美しさと讃えられます。
天守群は、大天守に乾小天守が渡櫓で連結、さらに辰巳櫓と月見櫓が接する複合連結式の構成で、その複雑さと組み合わせの妙は美的にも素晴らしい仕上がりです。
西側と南側からではまったく違った外観を見られるのも評判です。西面は無骨で単調な姿になるのに対し、南面は明るく開放的な姿になっています。この異なる天守の表情も松本城の魅力の一つです。
この城の最大の見どころは、やはり現存天守でしょう。五重六階の現存天守としては最も古く、本来の黒漆塗りの下見板張による「黒い天守」を堪能できます。青い空・白い北アルプスと黒い天守が織り成す情景は息をのむ美しさと讃えられます。
天守群は、大天守に乾小天守が渡櫓で連結、さらに辰巳櫓と月見櫓が接する複合連結式の構成で、その複雑さと組み合わせの妙は美的にも素晴らしい仕上がりです。
西側と南側からではまったく違った外観を見られるのも評判です。西面は無骨で単調な姿になるのに対し、南面は明るく開放的な姿になっています。この異なる天守の表情も松本城の魅力の一つです。
松江城
北と西を山稜に囲まれ、南は宍道湖に守られて周囲は低湿地。この要害の地に建っているのが松江城です。
松江城は関が原の戦いの功により出雲に所領を与えられた堀尾吉晴が1607年から5年の歳月をかけて完成させました。その後、徳川家康の孫の松平直政が入城したのを機に、松平家10代にわたる居城となりました。
最大の注目ポイントは、山陰地方で唯一現存する天守であることです。四重五階の望楼型複合式天守で、平面規模は姫路城の次に広くなっています。外壁は古い様式の黒塗りの下見板に覆われた黒色になっており、そのどっしりとした無骨なフォルムは甲冑姿の古武士を彷彿とさせます。
正面中央にある入母屋破風は、千鳥が羽を広げたように見え、華やかさも感じさせます。そのため松江城は「千鳥城」とも呼ばれています。
最上階の望楼からは松江市街や宍道湖の絶景を楽しむことができます。
松江城は関が原の戦いの功により出雲に所領を与えられた堀尾吉晴が1607年から5年の歳月をかけて完成させました。その後、徳川家康の孫の松平直政が入城したのを機に、松平家10代にわたる居城となりました。
最大の注目ポイントは、山陰地方で唯一現存する天守であることです。四重五階の望楼型複合式天守で、平面規模は姫路城の次に広くなっています。外壁は古い様式の黒塗りの下見板に覆われた黒色になっており、そのどっしりとした無骨なフォルムは甲冑姿の古武士を彷彿とさせます。
正面中央にある入母屋破風は、千鳥が羽を広げたように見え、華やかさも感じさせます。そのため松江城は「千鳥城」とも呼ばれています。
最上階の望楼からは松江市街や宍道湖の絶景を楽しむことができます。
犬山城
中国四川省にある白帝城は「三国志」の舞台となった城として知られ、古来、多くの詩人に詠まれてきました。その白帝城の別称をもつ城が、愛知県と岐阜県の境に建っています。これが国宝の犬山城です。
木曽川を背にした標高88mの断崖上に静かに佇む三重四階の現存天守は木造天守としては日本最古です。この風景は確かに中国唐代の詩人・李白の詩にあう白帝城を思わせます。
しかし現在の静寂とは裏腹に、往時の犬山城は戦国合戦の舞台であり続けました。
1537年、織田信長の叔父、信康が築城すると信長が攻略し、美濃侵攻の拠点としました。その後、城主は目まぐるしく代わり、1584年の小牧・長久手の戦いでは豊臣秀吉と徳川家康・織田信雄の激戦地となりました。
天守と本丸を一番奥の断崖上、搦め手の真上に置く縄張(後堅固)にしてあるのは、背後から敵に攻められないようにするという築城の定石を踏まえたものです。戦国時代という時代がうんだ城といえるかもしれません。
天守からは木曽川や古い町並み、御嶽山や岐阜城などの絶景が堪能できます。
木曽川を背にした標高88mの断崖上に静かに佇む三重四階の現存天守は木造天守としては日本最古です。この風景は確かに中国唐代の詩人・李白の詩にあう白帝城を思わせます。
しかし現在の静寂とは裏腹に、往時の犬山城は戦国合戦の舞台であり続けました。
1537年、織田信長の叔父、信康が築城すると信長が攻略し、美濃侵攻の拠点としました。その後、城主は目まぐるしく代わり、1584年の小牧・長久手の戦いでは豊臣秀吉と徳川家康・織田信雄の激戦地となりました。
天守と本丸を一番奥の断崖上、搦め手の真上に置く縄張(後堅固)にしてあるのは、背後から敵に攻められないようにするという築城の定石を踏まえたものです。戦国時代という時代がうんだ城といえるかもしれません。
天守からは木曽川や古い町並み、御嶽山や岐阜城などの絶景が堪能できます。
















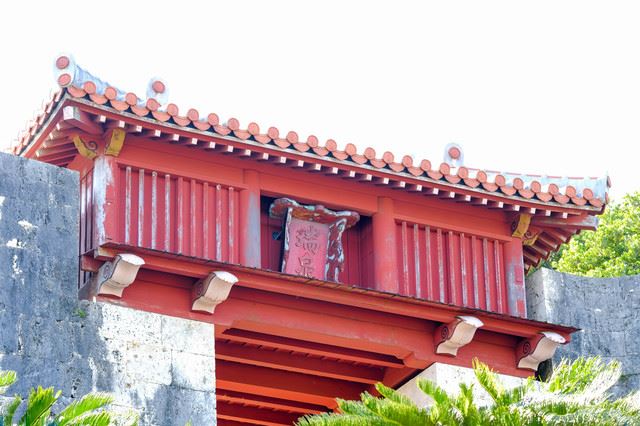






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

