土作りに大事?「バクテリア」の働きって?
関連キーワード

ガーデニングでは、土が重要とよく言われますよね。いい土を作ることが植物を上手に育てることにつながると、多くの人が耳にしているのではないでしょうか。そして、そんな土について考える際に「バクテリア」という言葉を聞いたことがある人もいると思います。
しかし、聞いたことはあっても実際に土のなかの「バクテリア」の役割については知らないことも多くあるのではないでしょうか。分からないことが多いのですが、いい土を目指すための「バクテリア」の働きについてまとめてみました。
しかし、聞いたことはあっても実際に土のなかの「バクテリア」の役割については知らないことも多くあるのではないでしょうか。分からないことが多いのですが、いい土を目指すための「バクテリア」の働きについてまとめてみました。
「バクテリア」とは?
「バクテリア」について調べると、「真正細菌」や「細菌」のことという風に書かれています。土のなかなかにいるたくさんの微生物のことを「土壌微生物」と言いますが、なんと1gに100万〜1000万もの数の「土壌微生物」がいるとのことです。そしてその「土壌微生物」のなかに「細菌」、つまり「バクテリア」も含まれています。
まず「土壌微生物」についてですが、その中身はと言うと、「細菌(バクテリア)」「放線菌」「糸状菌」「藻類」などがあり、実際にどのくらいの量が土のなかに含まれているのかという、生体量としては下記のような割合になっています。
「糸状菌」100〜1500(kg/10a)kg/10a)
「細菌(バクテリア)」40〜500(kg/10a)※大きさが小さいので数は最も多い
「放線菌」40〜500(kg/10a)
「藻類」1〜50(kg/10a)
そして、実はこの割合こそが大事と言われており、バランスが取れた割合になっています。このなかで細菌(バクテリア)は大きさとしては一番小さく、数としては一番多くいる「土壌微生物」となっています。
まず「土壌微生物」についてですが、その中身はと言うと、「細菌(バクテリア)」「放線菌」「糸状菌」「藻類」などがあり、実際にどのくらいの量が土のなかに含まれているのかという、生体量としては下記のような割合になっています。
「糸状菌」100〜1500(kg/10a)kg/10a)
「細菌(バクテリア)」40〜500(kg/10a)※大きさが小さいので数は最も多い
「放線菌」40〜500(kg/10a)
「藻類」1〜50(kg/10a)
そして、実はこの割合こそが大事と言われており、バランスが取れた割合になっています。このなかで細菌(バクテリア)は大きさとしては一番小さく、数としては一番多くいる「土壌微生物」となっています。
「土壌微生物」は多様性とバランスを保っている?
土のなかに100万〜1000万もの「土壌微生物」がいるということにはまず驚かされますよね。そして、それら土壌微生物同士が互いの微生物の生育を阻害する物質を作り、スペースを奪い合いながらもうまく土のなかのバランスを保っているというのもまた不思議な話です。
お互いに増減を繰り返しながらその種類と数のバランスを保っています。こうした「土壌微生物」の多様性がいい土と呼ばれるものになります。この多様性によって植物の病気を防ぎ、成長が促進されているというのですから、まさに縁の下の力持ちなのですね。この小さくてもたくさんの種類と数の「土壌微生物」が植物が育つことを支えていて、自然の力はすごいと改めて思いますね。
お互いに増減を繰り返しながらその種類と数のバランスを保っています。こうした「土壌微生物」の多様性がいい土と呼ばれるものになります。この多様性によって植物の病気を防ぎ、成長が促進されているというのですから、まさに縁の下の力持ちなのですね。この小さくてもたくさんの種類と数の「土壌微生物」が植物が育つことを支えていて、自然の力はすごいと改めて思いますね。
例えば、森のなかに行くと落ち葉がいっぱい落ちていますが、落ち葉や動物の糞尿を分解するのが「バクテリア」などの「土壌微生物」だと言われています。それらを分解して植物の栄養になる「窒素」にする働きをしています。とっても小さな「細菌」と言っても大事な役割の「細菌」が「バクテリア」なのです。
連作がNGなのは「土壌微生物」と関係がある?
よく言われるのが同じ植物を続けて植えるとよく育たなくなると言われますよね。「連作障害」などと言われます。これも実は土が関係していて、「土壌微生物」が連作をすることでバランスを崩す事が原因とされています。
連作をすると土の養分が消耗し、同じ植物や作物を育てると「土壌微生物」の多様性が損なわれ、病原菌が増える仕組みだと言われており、ある特定の植物や作物を育て続けると、特定の病原菌が増えて「土壌微生物」のバランスにより防ぐことができなくなり、病気になったりするということになると言うのです。
「土壌微生物」のバランス、その多様性を大事にするということがいかに大切なことかが分かります。
連作をすると土の養分が消耗し、同じ植物や作物を育てると「土壌微生物」の多様性が損なわれ、病原菌が増える仕組みだと言われており、ある特定の植物や作物を育て続けると、特定の病原菌が増えて「土壌微生物」のバランスにより防ぐことができなくなり、病気になったりするということになると言うのです。
「土壌微生物」のバランス、その多様性を大事にするということがいかに大切なことかが分かります。
土に与える肥料との関係は?
土に与える肥料との関係はどうかと言うと、実はこの「土壌微生物」の力を助けるために肥料を土に与えます。「土壌微生物」が土中の有機物を分解しますが、その働きを助けて養分を植物が取り込みやすくするための働きをするのが肥料です。
肥料と「土壌微生物」の関係はそんな関係となっていて、自然のなかの「土壌微生物」の力を助けるのが肥料ということになります。
肥料と「土壌微生物」の関係はそんな関係となっていて、自然のなかの「土壌微生物」の力を助けるのが肥料ということになります。
「バクテリア」の偉大な働き、そのバランス力!
バクテリアと言う小さな細菌をはじめとした「土壌微生物」がたくさんいてそれらがいっぱいあるという多様性とそのバランスが保たれていることによって植物が病気になったりを防いでくれたり、土中の有機物を分解するという偉大な働きをしてくれるのです。
私達には目に見えない小さな世界のそうした働きが豊かな土を作り、植物を育てる仕組みが作っています。「バクテリア」や「細菌」というと何だかこわい危ないもののように思いますが、そうした働きによって植物の生育が促進されています。
私達が自然の仕組みを知ることでそれを助けたりすることもでき、いい植物を育てることができるようになります。まずはガーデニングの第一歩としていい土について知ること、そしてそこで働く「バクテリア」などの多くの「土壌微生物」について知ることも重要ということになりますよね。
私達には目に見えない小さな世界のそうした働きが豊かな土を作り、植物を育てる仕組みが作っています。「バクテリア」や「細菌」というと何だかこわい危ないもののように思いますが、そうした働きによって植物の生育が促進されています。
私達が自然の仕組みを知ることでそれを助けたりすることもでき、いい植物を育てることができるようになります。まずはガーデニングの第一歩としていい土について知ること、そしてそこで働く「バクテリア」などの多くの「土壌微生物」について知ることも重要ということになりますよね。
よい土を作ってくれるいいバクテリアを増やすには

ベランダや庭・菜園を利用して、自分で花や野菜を育てて収穫も楽しむ人が増えています。
植物を上手に育てるには「まずは土づくりから」と言いますが、そもそも「よい土」とはどういう土なのでしょう。
いい土を作ってくれるのは「善いバクテリア」だと言われても、ピンときませんが、この機会に「善いバクテリア」について、考えてみましょう。
植物を上手に育てるには「まずは土づくりから」と言いますが、そもそも「よい土」とはどういう土なのでしょう。
いい土を作ってくれるのは「善いバクテリア」だと言われても、ピンときませんが、この機会に「善いバクテリア」について、考えてみましょう。
ふかふかの土を作るのは土のなかのバクテリア
植物を育てるのに最適なふかふかの「よい土」は、単にふかふかというだけでは十分とは言えません。
手触りがしっとりするくらいの丁度いいくらいの水分を含んだ状態で、土をぎゅっと握ったとき、軽くひとまとまりになりながら、崩そうとするとほろほろ崩れるくらいの状態が最適だと言われています。
完全なさらさらふわふわではなく、ある程度粒状の塊になっている部分もある状態が寄り集まってできていて、それでいて柔らかい状態が保てるのが理想です。
スプーン1杯の土のなかには細菌やウイルス・カビといった微生物が10億個いると言われています。
この微生物のうち、納豆菌・放線菌・乳酸菌・光合成細菌などの細菌類のことを「バクテリア」と言い、バクテリアが堆肥や食物繊維・タンパク質などを分解したり、土を粒状にまとめる「団粒化」を行ったりしています。
肥料分がたっぷりと含まれていて、ふわふわなのに粒状に寄り集まった土は、土のなかのバクテリアが作ってくれます。
手触りがしっとりするくらいの丁度いいくらいの水分を含んだ状態で、土をぎゅっと握ったとき、軽くひとまとまりになりながら、崩そうとするとほろほろ崩れるくらいの状態が最適だと言われています。
完全なさらさらふわふわではなく、ある程度粒状の塊になっている部分もある状態が寄り集まってできていて、それでいて柔らかい状態が保てるのが理想です。
スプーン1杯の土のなかには細菌やウイルス・カビといった微生物が10億個いると言われています。
この微生物のうち、納豆菌・放線菌・乳酸菌・光合成細菌などの細菌類のことを「バクテリア」と言い、バクテリアが堆肥や食物繊維・タンパク質などを分解したり、土を粒状にまとめる「団粒化」を行ったりしています。
肥料分がたっぷりと含まれていて、ふわふわなのに粒状に寄り集まった土は、土のなかのバクテリアが作ってくれます。
善いバクテリアVS悪いバクテリア
バクテリアにもいろいろあり、植物の生育にぴったりの条件を作ってくれる「善いバクテリア」があれば、腐敗させ異臭を放ったり、立ち枯れ病や軟腐病を起こさせる「悪いバクテリア」も存在しています。
善いバクテリアが増え、悪いバクテリアが少なくなるような環境を作れば、手を掛けなくてもすくすくと植物が育つようになります。
善いバクテリアは空気をしっかりと含んだ状態でよく働きます。悪いバクテリアは逆に、空気が少ない酸欠の状態を好みます。
土のなかにしっかりと酸素が取り込まれるように、土や堆肥をかき混ぜたり耕したりすることで、悪臭がしたり腐敗したりすることを防いで、善いバクテリアがしっかりと働けるようにします。
古い土をそのまま植物の栽培に利用するとうまく育たないのは、土のなかの栄養素のバランスや善いバクテリアと悪いバクテリアのバランスが崩れているのが原因です。
善いバクテリアが増え、悪いバクテリアが少なくなるような環境を作れば、手を掛けなくてもすくすくと植物が育つようになります。
善いバクテリアは空気をしっかりと含んだ状態でよく働きます。悪いバクテリアは逆に、空気が少ない酸欠の状態を好みます。
土のなかにしっかりと酸素が取り込まれるように、土や堆肥をかき混ぜたり耕したりすることで、悪臭がしたり腐敗したりすることを防いで、善いバクテリアがしっかりと働けるようにします。
古い土をそのまま植物の栽培に利用するとうまく育たないのは、土のなかの栄養素のバランスや善いバクテリアと悪いバクテリアのバランスが崩れているのが原因です。
堆肥などはバクテリアが分解するから肥料になる

堆肥や腐葉土などの有機肥料はそのままでは植物には吸収されません。バクテリアが有機肥料を分解することで肥料分として植物が根で吸収できるようになります。
化学肥料の効果に即効性があるのに対して、有機肥料がすぐには効いてこないのは分解するのに時間が掛かるためで、効いてくるのに時間を要する代わりに、バクテリアがじっくりと分解してくれるので長い間効果が続きます。
化学肥料の効果に即効性があるのに対して、有機肥料がすぐには効いてこないのは分解するのに時間が掛かるためで、効いてくるのに時間を要する代わりに、バクテリアがじっくりと分解してくれるので長い間効果が続きます。
善いバクテリアを増やす昔ながらの知恵
天日干しして消毒
栽培が終わった土から根やごみなどを取り除いた後、全体に軽く水を含ませてから黒いビニール袋に入れて、なるべく広げるようにしながら天日干しします。夏の暑い日が特に有効で、日光消毒と蒸気消毒が同時にできます。
水ではなく、80℃以上の熱湯をかけると消毒効果が高くなり、虫も退治できます。1ヵ月程度放置してから新しい土や腐葉土などを2〜3割程度混ぜて再利用します。
水ではなく、80℃以上の熱湯をかけると消毒効果が高くなり、虫も退治できます。1ヵ月程度放置してから新しい土や腐葉土などを2〜3割程度混ぜて再利用します。
天地返し

家庭菜園や庭の場合、土を深めに掘り起こして、上下をひっくり返しておく「天地返し」を、秋口〜冬に行います。草の種も地中深くでは芽が出にくく、冬の凍結と解凍が繰り返されることで土質がよくなり、病害虫も駆除できます。
天地返ししたあと、土の上に苦土石灰などをまいておき、酸性寄りになった土のpHを調整することが多いのですが、わずかで十分なのでまきすぎに注意しましょう。
土の状態が悪いときに消毒のため、80℃以上の熱湯をかけておくのもオススメです。
天地返ししたあと、土の上に苦土石灰などをまいておき、酸性寄りになった土のpHを調整することが多いのですが、わずかで十分なのでまきすぎに注意しましょう。
土の状態が悪いときに消毒のため、80℃以上の熱湯をかけておくのもオススメです。
枝葉や草も一緒にすきこむ
野菜を栽培した後、抜いた枝葉は小さく刻んでから土に埋め込むと、ミミズやバクテリアが分解してくれるため、ふかふかの土の材料になっていきます。
抜いた草も畑や庭の隅に積んでおくと、下の方から徐々にミミズやバクテリアが分解してくれるため、いつの間にか栄養豊富な土に生まれ変わっています。
土から吸収された栄養分で枝葉や草が育ち、これらをまた土に返すことで分解され、その栄養分が土に吸収されます。これだけで肥料分としては十分量とは言えませんが、善い土を作る栄養素の一部に生まれ変わります。
抜いた草も畑や庭の隅に積んでおくと、下の方から徐々にミミズやバクテリアが分解してくれるため、いつの間にか栄養豊富な土に生まれ変わっています。
土から吸収された栄養分で枝葉や草が育ち、これらをまた土に返すことで分解され、その栄養分が土に吸収されます。これだけで肥料分としては十分量とは言えませんが、善い土を作る栄養素の一部に生まれ変わります。
まとめ
土のなかには大量の微生物が含まれていて、そのなかには善いバクテリアもいれば悪いバクテリアもいますが、善いバクテリアを増やして効果的に働いてもらうために、土にしっかりと空気を含ませるようにしましょう。
善いバクテリアが堆肥や腐葉土を植物が吸収できる栄養素に分解してくれ、土をちょうどいい粒状の、空気を含みやすい団粒状にしてくれます。
殺虫剤などの農薬を散布すると害虫が駆除できますが、土のなかの微生物まで駆除してしまうため、土のなかのバクテリアのバランスも崩れ、善いバクテリアがしっかりと働けない環境になってしまいます。
善いバクテリアが堆肥や腐葉土を植物が吸収できる栄養素に分解してくれ、土をちょうどいい粒状の、空気を含みやすい団粒状にしてくれます。
殺虫剤などの農薬を散布すると害虫が駆除できますが、土のなかの微生物まで駆除してしまうため、土のなかのバクテリアのバランスも崩れ、善いバクテリアがしっかりと働けない環境になってしまいます。
ビオトープ・アクアリウムの澄んだ水はバクテリアが決め手

軒先のスイレン鉢に水草が浮かび、なかをのぞくと澄んだ水中をメダカが泳いでいる涼し気な情景に出会うと、夏の暑さが和らぐような気がしますね。
細いエアホースがポンプとつないであって空気を水のなかに送り込んでいることもありますが、エアレーションがなにもないのに澄んだ水が保たれていることもあります。
澄んだ水のなかにはバクテリアが豊富にいて、水質を浄化しています。魚や水草が育ちやすい水質を作るバクテリアについて考えてみましょう。
細いエアホースがポンプとつないであって空気を水のなかに送り込んでいることもありますが、エアレーションがなにもないのに澄んだ水が保たれていることもあります。
澄んだ水のなかにはバクテリアが豊富にいて、水質を浄化しています。魚や水草が育ちやすい水質を作るバクテリアについて考えてみましょう。
ビオトープやアクアリウムって何?
スイレン鉢や水槽などで魚を飼うのはむずかしそう、世話や水替えが大変そう、と思われるかも知れませんが、魚の生育に最適な水質ができ上がり、狭いところで大量に魚を飼うといった暴挙に出なければきれいな水質が長く維持でき、それほど頻繁な水替えは必要ありません。
「アクアリウム」は水生生物を飼育する設備、つまり、熱帯魚・めだか・金魚などの魚や、スイレンや浮草・シダなどの水草を飼育するセット全般をさしています。 魚は淡水魚でも海水魚でもアクアリウムになります。
「ビオトープ」はドイツ語では「Biotopビオトープ」、英語では「Biotopeバイオトープ」と言い、「生物の生息空間」を意味し、自然な生態系を構築させる場所として、絶滅の恐れのあるホタルの生息地やメダカやドジョウなども住める環境を守ることなどをさしていますが、現在はベランダでもできる「メダカと水草栽培セット」のようなものもビオトープと考えられています。
分かりやすく分類するとすれば、水槽などで魚や水草を飼育しているものをアクアリウム、そのうちの、自然のせせらぎを再現したような野趣あふれるものをビオトープと言うように、ざっくりと考えればよいのではないかと思います。
「アクアリウム」は水生生物を飼育する設備、つまり、熱帯魚・めだか・金魚などの魚や、スイレンや浮草・シダなどの水草を飼育するセット全般をさしています。 魚は淡水魚でも海水魚でもアクアリウムになります。
「ビオトープ」はドイツ語では「Biotopビオトープ」、英語では「Biotopeバイオトープ」と言い、「生物の生息空間」を意味し、自然な生態系を構築させる場所として、絶滅の恐れのあるホタルの生息地やメダカやドジョウなども住める環境を守ることなどをさしていますが、現在はベランダでもできる「メダカと水草栽培セット」のようなものもビオトープと考えられています。
分かりやすく分類するとすれば、水槽などで魚や水草を飼育しているものをアクアリウム、そのうちの、自然のせせらぎを再現したような野趣あふれるものをビオトープと言うように、ざっくりと考えればよいのではないかと思います。
バクテリアは空気中などどこにでもいる
1gの土のなかに1億個のバクテリアが住んでいるように、バクテリアは空気中にもどこにでも住んでいます。
アクアリウムやビオトープを作る上で欠かせない生物の住みやすい水環境は、単にごみをフィルターで取り除いただけでは作れません。
魚を飼うと当然ですがふんをするので、水中に有機物や有害なアンモニアなどが増え、これらの有機物を分解してくれるバクテリアがたくさん生息していないと、魚がバタバタ死んでしまいます。
水中に豊富にバクテリアが生息してはじめて生物の住みやすい水環境になります。
アクアリウムやビオトープを作る上で欠かせない生物の住みやすい水環境は、単にごみをフィルターで取り除いただけでは作れません。
魚を飼うと当然ですがふんをするので、水中に有機物や有害なアンモニアなどが増え、これらの有機物を分解してくれるバクテリアがたくさん生息していないと、魚がバタバタ死んでしまいます。
水中に豊富にバクテリアが生息してはじめて生物の住みやすい水環境になります。
ろ過バクテリアなど有益なバクテリアは好気性
生物の生育に最適な水質を作ってくれるろ過バクテリアなどの有益なバクテリアは、酸素を好む「好気性」のものが多く、酸素が嫌いな「嫌気性」のバクテリアの多くは、悪臭を出したり腐敗させるバクテリアです。
水槽の水を循環させた方が澄んでいて、見た目にもいい水の状態を保てたり魚臭くなったりしないのは、水中に空気がたくさん含まれて、ろ過バクテリアが豊富に存在してしっかりと働けるからです。
エアレーションしていないスイレン鉢のビオトープでは、魚の数や与えるえさを極力少なくして水草をたくさん入れた方が、酸素が豊富に水中に含まれるため、バクテリアがうまく働いてよい水質を保てます。
水槽の水を循環させた方が澄んでいて、見た目にもいい水の状態を保てたり魚臭くなったりしないのは、水中に空気がたくさん含まれて、ろ過バクテリアが豊富に存在してしっかりと働けるからです。
エアレーションしていないスイレン鉢のビオトープでは、魚の数や与えるえさを極力少なくして水草をたくさん入れた方が、酸素が豊富に水中に含まれるため、バクテリアがうまく働いてよい水質を保てます。
底に入れるのは砂利など粒状のものがオススメ
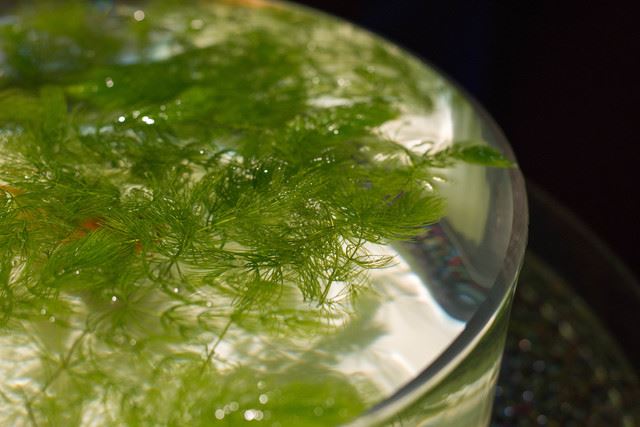
ビオトープでは田んぼの土を再現するために土を入れたほうがいいと思いがちですが、アクアリウム全般において、砂利などの粒状のものがオススメです。
土を入れると、土のなかの有機物や肥料分が豊富にありすぎて水質を悪化させ、ポンプを使うとポンプが詰まって故障しやすくなります。
砂利やセラミックなどの粒状のものは、有機物や肥料分を増やさず、表面に空いた無数の穴がバクテリアを増やすのを助ける働きもあるため、水質をきれいに保ちやすくなります。
赤玉土なども粒状ですが、細かなみじんも含まれ、次第に粒が崩れて土と同じになるので、安価ですが扱いやすい資材とは言えません。
土を入れると、土のなかの有機物や肥料分が豊富にありすぎて水質を悪化させ、ポンプを使うとポンプが詰まって故障しやすくなります。
砂利やセラミックなどの粒状のものは、有機物や肥料分を増やさず、表面に空いた無数の穴がバクテリアを増やすのを助ける働きもあるため、水質をきれいに保ちやすくなります。
赤玉土なども粒状ですが、細かなみじんも含まれ、次第に粒が崩れて土と同じになるので、安価ですが扱いやすい資材とは言えません。
買ったばかりの水槽にはバクテリアが少ない
買ったばかりの水槽の底に砂利を入れて、水草をセッティングし、カルキ抜きを入れるか一日置いておいた日向水を入れ、ポンプで循環させたところに熱帯魚やメダカなどを入れてアクアリウムをスタートさせると、はじめのうちはバタバタと魚が死んでしまいます。
これは水に悪いものや病原菌が入っているわけではなく、水中に有機物やアンモニアを分解してくれるバクテリアが十分に存在していないためです。 バクテリアが豊富な「強い水」を作ってからアクアリウムをスタートさせる必要があります。
これは水に悪いものや病原菌が入っているわけではなく、水中に有機物やアンモニアを分解してくれるバクテリアが十分に存在していないためです。 バクテリアが豊富な「強い水」を作ってからアクアリウムをスタートさせる必要があります。
バクテリアが豊富な「強い水」を作るには

まだ新しい水槽でも、魚を入れない状態で1週間ほど水を循環させてからなら、空気中のバクテリアが水にどんどん溶けこんで増えてきているので、水質がある程度向上しています。
そのあとから、まずは2〜3匹小さな魚を入れてみて、1週間ごとに水を1/3程度入れ替える作業を続けてどんどんバクテリアを増やしていきます。
1ヵ月半ほどたつと、ろ過バクテリアなどの有益なバクテリアが豊富に含まれる「強い水」が出来上がるので、徐々に魚も増やせるようになります。
水草だけを育てる場合も、最初に2〜3匹の小さな魚を入れたほうが、水草にもよい環境が素早く出来上がります。
そのあとから、まずは2〜3匹小さな魚を入れてみて、1週間ごとに水を1/3程度入れ替える作業を続けてどんどんバクテリアを増やしていきます。
1ヵ月半ほどたつと、ろ過バクテリアなどの有益なバクテリアが豊富に含まれる「強い水」が出来上がるので、徐々に魚も増やせるようになります。
水草だけを育てる場合も、最初に2〜3匹の小さな魚を入れたほうが、水草にもよい環境が素早く出来上がります。
水槽の水濁りはバクテリアの死骸
まだ新しいの水槽の水を1/3程度かえたとき、水が一気に白く濁ることがあります。これは、バクテリアの死骸で、バクテリアが大量に死んだために起こっています。水質がまだ安定していないために起こりやすくなります。
バクテリアがある程度増えてきたので起こったことなので、そうなればいい水環境が出来上がった強い水になるまであと少しです。
バクテリアがある程度増えてきたので起こったことなので、そうなればいい水環境が出来上がった強い水になるまであと少しです。
バクテリア剤はどんなときに有効?
まだバクテリアが十分に増えていない新しい水槽や、餌のあげ過ぎなどが原因でバクテリアのバランスが悪くなった水槽では、水質が悪化しやすく、魚が病気がちになったりバタバタと死んでしまうことがあります。
魚が病気になると「薬を買ってこなくては!」「水を全部入れ替えなくては!」と思いがちですが、そうすることでますます水質が悪化してしまいます。
こんなときに一気に水質を改善してくれるものが市販の「バクテリア剤」です。開封して水に入れることで水中のバクテリアが増え、水質が短期間で改善されます。
十分に生環境が整って、「強い水」になったバクテリアが豊富な状態では、バクテリア剤を加えたとしてもメリットはほとんどありませんが、水質が悪化したようなときには有効です。
監修:きなりのすもも
16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、
ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、
一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。
魚が病気になると「薬を買ってこなくては!」「水を全部入れ替えなくては!」と思いがちですが、そうすることでますます水質が悪化してしまいます。
こんなときに一気に水質を改善してくれるものが市販の「バクテリア剤」です。開封して水に入れることで水中のバクテリアが増え、水質が短期間で改善されます。
十分に生環境が整って、「強い水」になったバクテリアが豊富な状態では、バクテリア剤を加えたとしてもメリットはほとんどありませんが、水質が悪化したようなときには有効です。
監修:きなりのすもも
16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、
ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、
一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

