茶道で使われる和菓子の種類はどんなものか

「お茶とお菓子」と並び称されるように、茶道では、お菓子もお茶とともに欠かせない大切なものです。お菓子は、いつの時代から、お茶とともにいただくものになったのでしょうか。改めて、茶道で使われるお菓子について、歴史や種類をまとめてみました。
合わせて、ちょっとしたお茶席でも慌てないように、菓子のいただき方もご案内します。
合わせて、ちょっとしたお茶席でも慌てないように、菓子のいただき方もご案内します。
茶道と菓子の歴史
砂糖をふんだんに使った甘いお菓子が一般に普及するようになるのは、江戸時代に入ってからのことです。千利休が活躍した桃山時代には、今のような甘い菓子が茶道で使われることはありませんでした。利休の頃までの茶会記を調べると、菓子として、栗、柿などの果物や、椎茸、煎り豆、昆布など、今は菓子とは呼ばない食材が供されていました。なお、「麩の焼き」と呼ばれる菓子も使われた記録が残っていますが、これは、小麦粉を水で溶いて薄い円盤状に広げて鉄板で焼き味噌を塗ってまいた菓子で、利休が考案して、自らも好んだと伝わっています。
砂糖を使った菓子は、室町時代から作られてはいましたが、たいへんな高級品で、一部の身分の高い人だけが楽しむものでした。江戸時代の中期になり、国内での砂糖の生産が増加すると、砂糖を使った多種多様な菓子が作られ、庶民の口にも入るものとなっていきました。この時期からは、茶道でも、菓子として饅頭や羊羹が使われるようになっていきました。
お菓子の老舗と呼ばれる店の多数は、江戸時代の創業です。京菓子の老舗といわれる鶴屋吉信は、江戸時代の後期の創業、尾州徳川家の御用菓子屋だった両口屋是清も17世紀の創業です。大阪の老舗和菓子屋「鶴屋八幡」は、元禄時代の創業の「虎屋伊織」が前身です。 虎屋伊織の様子は、「東海道中膝栗毛」に登場し、『摂津名所図会』にも、旅人が土産を買い求める盛況ぶりが描かれています。
ただし、羊羹で有名な「とらや」は、創業が室町時代の京都に遡ります。京都の公家を顧客として発展してきたため、明治に入り、御所が東京に移転すると自らの店も東京に移しました。
砂糖を使った菓子は、室町時代から作られてはいましたが、たいへんな高級品で、一部の身分の高い人だけが楽しむものでした。江戸時代の中期になり、国内での砂糖の生産が増加すると、砂糖を使った多種多様な菓子が作られ、庶民の口にも入るものとなっていきました。この時期からは、茶道でも、菓子として饅頭や羊羹が使われるようになっていきました。
お菓子の老舗と呼ばれる店の多数は、江戸時代の創業です。京菓子の老舗といわれる鶴屋吉信は、江戸時代の後期の創業、尾州徳川家の御用菓子屋だった両口屋是清も17世紀の創業です。大阪の老舗和菓子屋「鶴屋八幡」は、元禄時代の創業の「虎屋伊織」が前身です。 虎屋伊織の様子は、「東海道中膝栗毛」に登場し、『摂津名所図会』にも、旅人が土産を買い求める盛況ぶりが描かれています。
ただし、羊羹で有名な「とらや」は、創業が室町時代の京都に遡ります。京都の公家を顧客として発展してきたため、明治に入り、御所が東京に移転すると自らの店も東京に移しました。
茶道で使われるお菓子の種類
茶道で提供されるお菓子には、日持ちがあまりしない主菓子と、落雁などの日持ちがする干菓子があります。
正式な茶会では、主菓子はどろりと練った濃茶の前にいただき、干菓子はさらりとした薄茶と取り合わせられます。 ただし、最近では、薄茶しか出ない大寄せの茶会では、主菓子を合わせることが多いようです。
お菓子は季節に応じた形や色どりのものが選ばれます。春には、季節の花の形をしたもの、夏は羊羹など涼しげに見えるもの、秋には紅葉を表したものなど・・。菓子で季節感を表現しています。
正式な茶会では、主菓子はどろりと練った濃茶の前にいただき、干菓子はさらりとした薄茶と取り合わせられます。 ただし、最近では、薄茶しか出ない大寄せの茶会では、主菓子を合わせることが多いようです。
お菓子は季節に応じた形や色どりのものが選ばれます。春には、季節の花の形をしたもの、夏は羊羹など涼しげに見えるもの、秋には紅葉を表したものなど・・。菓子で季節感を表現しています。
主菓子の種類といただき方
主菓子の多くは餡子を使っています。
基本は饅頭で、皮に大和芋を用いた「薯蕷饅頭」が定番です。
色をつけた餡を裏ごしして、栗のイガのようにした「きんとん」は菜の花や紫陽花など、季節の花を表現したものが豊富です。色合いも華やかですが、口のなかで軽やかに溶けて口当たりがよいのが特徴です。
着色した白餡につなぎをいれた「練り切り」は、自由に形を作れるため、季節の花、柿などの果物、色付いた葉など様々な姿を表現することができます。滑らかな餡としっかりとした甘さがお抹茶によくあいます。
夏には、見た目も涼しげでのどごしもよい寒天や葛・ゼリーを使った錦玉羹などが好まれます。
主菓子は、正式には縁高という重箱のような正方形の塗りの器に、一人一本ずつ黒文字(菓子楊枝)が添えられて運び出されます。略式の場合は、蓋のついた陶器か塗り物の食籠、あるいは陶器の菓子鉢に盛られます。上座の正客から懐紙を取り出して、一つずつ菓子をとり、次の人に菓子器をまわします。
基本は饅頭で、皮に大和芋を用いた「薯蕷饅頭」が定番です。
色をつけた餡を裏ごしして、栗のイガのようにした「きんとん」は菜の花や紫陽花など、季節の花を表現したものが豊富です。色合いも華やかですが、口のなかで軽やかに溶けて口当たりがよいのが特徴です。
着色した白餡につなぎをいれた「練り切り」は、自由に形を作れるため、季節の花、柿などの果物、色付いた葉など様々な姿を表現することができます。滑らかな餡としっかりとした甘さがお抹茶によくあいます。
夏には、見た目も涼しげでのどごしもよい寒天や葛・ゼリーを使った錦玉羹などが好まれます。
主菓子は、正式には縁高という重箱のような正方形の塗りの器に、一人一本ずつ黒文字(菓子楊枝)が添えられて運び出されます。略式の場合は、蓋のついた陶器か塗り物の食籠、あるいは陶器の菓子鉢に盛られます。上座の正客から懐紙を取り出して、一つずつ菓子をとり、次の人に菓子器をまわします。
干菓子の種類
干菓子は、文字通り、水分を含まない菓子で日持ちがするものです。煎餅、型に打ち込んで作る打物、砂糖を煮つめた飴である有平などが好んで使われます。
茶道で使われる煎餅は、醤油味の香ばしいものではなく、甘くて軽い麩焼きせんべいです。落雁は、米などから作った粉に水飴や砂糖を混ぜて着色した菓子です。型で成形するので、果物・花、鳥など様々な形で、目も楽しませてくれるお菓子です。有平は、色鮮やかな飴細工で、千代結びなど可愛らしい形のものが豊富です。
干菓子は、二種類を出すのが原則で、塗物の干菓子盆に人数分以上の数の菓子を盛り合わせます。この際、整然と並べるよりも、「一つつまみ食いをしても、ばれない」ような感じで、さり気なく盛り込むことがコツと言われています。干菓子器も正客から順番に回って行きますので、客は自分の番になったら、懐紙にそれぞれの種類を、一つずつとっていただきます。
茶道で使われる煎餅は、醤油味の香ばしいものではなく、甘くて軽い麩焼きせんべいです。落雁は、米などから作った粉に水飴や砂糖を混ぜて着色した菓子です。型で成形するので、果物・花、鳥など様々な形で、目も楽しませてくれるお菓子です。有平は、色鮮やかな飴細工で、千代結びなど可愛らしい形のものが豊富です。
干菓子は、二種類を出すのが原則で、塗物の干菓子盆に人数分以上の数の菓子を盛り合わせます。この際、整然と並べるよりも、「一つつまみ食いをしても、ばれない」ような感じで、さり気なく盛り込むことがコツと言われています。干菓子器も正客から順番に回って行きますので、客は自分の番になったら、懐紙にそれぞれの種類を、一つずつとっていただきます。
お菓子はお茶の前にいただくもの
茶道では、お菓子を食べ終わってから、お茶をいただきます。お抹茶が苦いと感じる方は、お菓子を一口、お抹茶一口と交互に口に入れたくなりますが、そういう頂き方はお勧めできません。
茶道にとっての菓子は、お茶の味を楽しむ為の「前菜」の位置付けで、あくまで主役は抹茶です。
因みにイタリア料理の正式なディナーでも、お菓子は先に食べ、その後、エスプレッソが振舞われます。 苦味が比較的に強い飲み物を楽しむ為には、まず甘いものを口にするのが、万国共通の楽しみ方なのかもしれません。
茶道にとっての菓子は、お茶の味を楽しむ為の「前菜」の位置付けで、あくまで主役は抹茶です。
因みにイタリア料理の正式なディナーでも、お菓子は先に食べ、その後、エスプレッソが振舞われます。 苦味が比較的に強い飲み物を楽しむ為には、まず甘いものを口にするのが、万国共通の楽しみ方なのかもしれません。










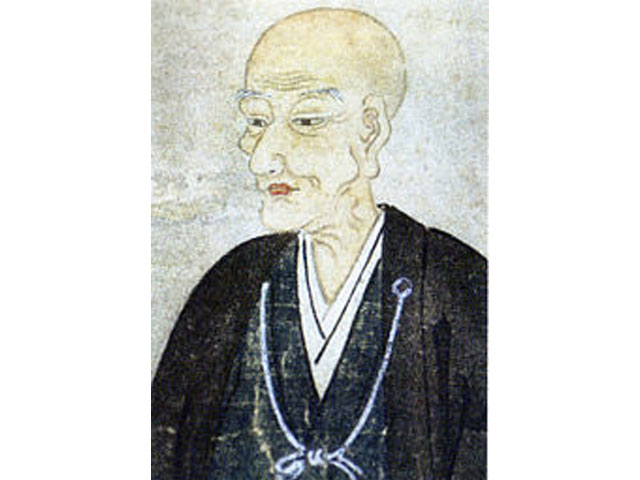



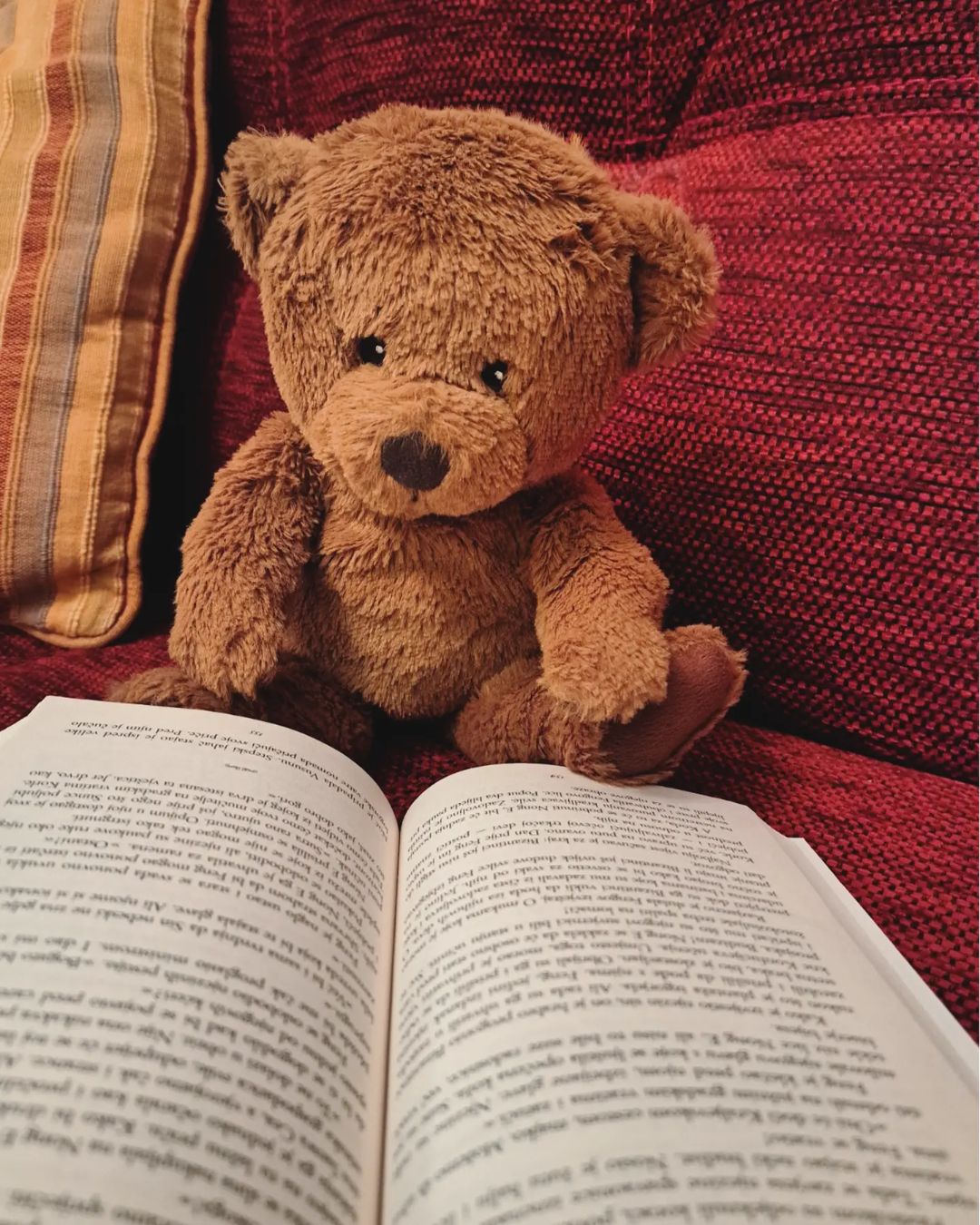









![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

